「女子大」×女子大 ~シリーズ女子大で学ぶ⑩
2025/04/02
シリーズ「女子大で学ぶ」では、人間関係学科の教員が、女子大学で学ぶ意義を考え、発信しています。第10回は、特別編。女子大学をテーマにした卒業論文「女子大学の存在意義と課題」※1を今年3月に提出したKさん(記事執筆当時人間文化学類 人間関係専攻※24年生)に卒論執筆後の感想を寄せてもらいました。
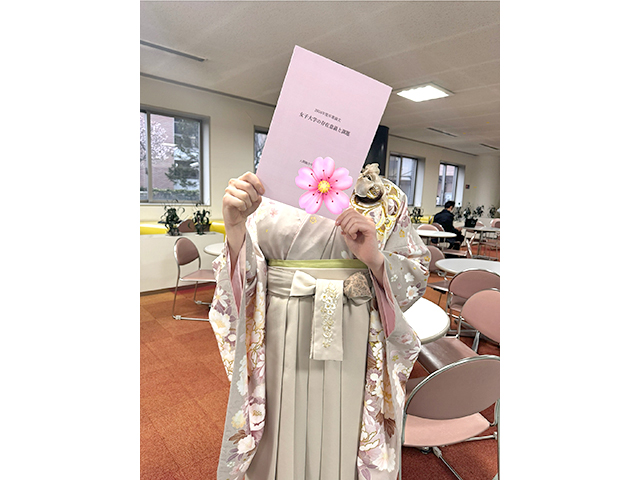
Kさん(卒業式当日、卒業論文を持って)
私がこの大学に入った理由は、女子大だから、家から近いからという軽い気持ちでした。女子大を選んだのは、高校生のときの先生が女子大出身で、女子大は面倒見がいいからと薦められたのがきっかけです。
実際に入ってみると、共学であった中学・高校よりも女子だけの空間は想像以上に居心地が良く、女子大がすごく好きになりました。しかし、大学で学んでいくにつれ、世の中がジェンダー平等へと向かおうとするなか、女子大は不要なのではないかとの意見があることを知りました。そこで「女子大学の存在意義と課題」というテーマで卒業論文を書くことにしました。
卒業論文を執筆してみて、現代社会においては依然として男女間格差が根強く残っていることを知りました。そのような社会だからこそ、女子大学は大きな存在意義を有している、そして今後の社会においても必要であると感じました。
私自身のことを考えると、女子大学に4年間通い、ジェンダーをテーマにした講義でなくとも、女性の問題に関係した内容を学ぶことが多く、そのような点は女子大ならではの強みだったなと気付きます。また、高校時代の先生が「女子大は面倒見が良い」と言っていたように、女子大学は共学に比べて規模が小さく、まだ十分でないにしろ女性教員の数も(共学の大学に比して)比較的多いといえます。
私の学んだ駒沢女子大学の人間関係専攻においては、特に女性教員の割合が多いです。卒論を書いて知ったのですが、女子大の存在意義一つとして、ロールモデル(女性教員)の存在があり、それが女子学生に肯定的な作用を及ぼすことがわかっています。私も実際に女性の先生方と接しながら、その効果を強く感じました。
また一般に、近年の「男女平等」といわれる社会においては「女子大学は不要だ」という意見が増えてきていると言われます。でも調べていてわかったことは、「女子大不要論」は最近出てきたものではなく1900年代初頭から存在したということです。いつの時代も女子大や女子学生は批判の対象になりやすく、そんな社会だからこそ、女子教育に特化した場所が必要だったし、これからも必要なのではないかと感じました。
卒業論文を書いてみて、そして女子大に通った立場から、私は女子大がこれからもずっと残ってほしいと思います。
(人間文化学類 人間関係専攻 4年 Kさん)
- ※1 Kさんの卒業論文は、駒沢女子大学オープンキャンパス・人間関係学科のブースにてお手に取ってお読みいただくことが可能です。(卒業論文主査担当 大貫恵佳)
- ※2 「人間関係学科」の前身となる「人間文化学類 人間関係専攻」の先輩です。
“シリーズ「女子大で学ぶ」”について
このシリーズでは、人間関係学科の教員が、現代社会において女子大学で学ぶ意義を考え、発信しています。「もう男女で分ける時代じゃない、大事なのは“その人らしさ”」という考えに私たちも共感します。ただ、私たちは、そうした社会が実現するためにも、そうした社会で女性が生き抜いていくためにも、女性たちに寄り添った教育の場所が必要だと考えています。女子大学でさまざまな学生たちと接しながら、私たち教員が日々思うこと、考えていることについてお読みいただければ幸いです。
シリーズ「女子大で学ぶ」の記事
- ⑫横浜アンパンマンこどもミュージアム×女子大
- ⑪宇宙×女子大
- ⑩「女子大」×女子大
- ⑨学園祭×女子大
- ⑧チームワーク×女子大
- ⑦化粧×女子大
- ⑥恋愛×女子大
- ⑤学生に聞く「女子大のリアル」
- ④研究×女子大
- ③テーマパーク×女子大
- ②キャリア×女子大
- ①ジェンダー×女子大


