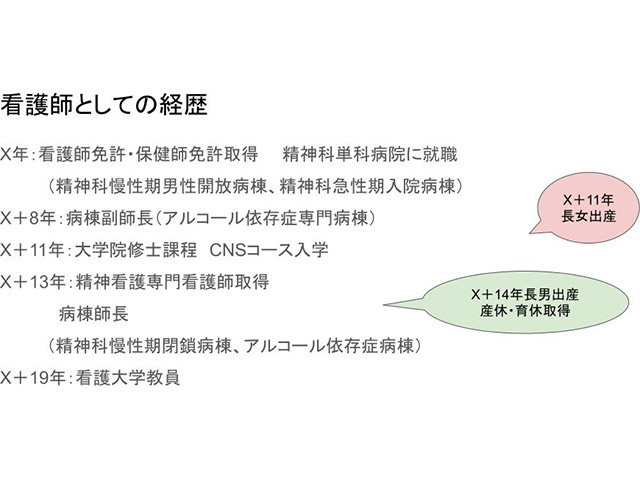シナリオシミュレーション演習を行いました(小児看護学方法論)
2025/08/25
小児看護学では、子どもへの看護を学習しています。3年生では、疾患や障害を持つ子どもの病院での看護の実際を学びます。今回は、3年生が7月に実施したシミュレーション演習についてご紹介します。
シミュレーション演習では、実際の病院の様子を再現して、モデル人形を使用して看護を実践していきます。使う物や子どもの状態、発言など、実際の病院で起こりそうなことを体験します。教員が子ども役となって、モデル人形の代わりにおしゃべりをしたり、モデル人形を動かしたりします。今回は、子どもが入院中生活をしているベッド周囲の整理・清掃、体温や呼吸回数等の測定、霧化した薬を口・鼻から吸ってもらう薬剤投与を実施しました。

ベッド周囲の整理・清掃時の様子
ーどこをどのように片付けたら良いかな?ー
ベッド周囲の整理・清掃では、大人の患者さんであれば、「お掃除させてください」と言えば、ある程度理解して協力していただけますが、子どもの場合そうもいきません。「作りかけのパズルは触っちゃだめ」と子どもに言われて困ったり、ベッドの柵を外すと子どもが落ちそうになってしまったり、使わなくなった酸素マスクが置いたままになっていたりします。いろいろな危険性を予測し、子どもにとってより安全で過ごしやすい環境を整えるにはどうしたらよいか、学生は一生懸命に考えていました。
バイタルサイン測定では、体温を正確に計るために体温計をきちんと脇の下に挟む、動かないでじっとしていることは子どもにとっては難しく、看護師の補助が必要なことを学びました。また、「呼吸音を聞かせてください」を子どもに分かりやすく伝えることも難しいところです。小児看護では聴診器を使って音を聞くことを「もしもし」と言ったりします。そういった子どもにわかりやすい表現を学ぶのもこの演習のねらいです。
吸入は薬を吸っている10分程度の間、子どもはじっとしていなくてはなりません。「つまんない」「ひま」という子どもに絵本を読み聞かせたり、一緒に塗り絵をしたりして、気を紛らわすことをディストラクションといいますが、そのディストラクションの実践も大切なポイントです。
事前学習をしても想像できていなかったり、事前には考えていても実際やろうとすると忘れてしまったりします。でも、学内だから失敗しても大丈夫。ここではたくさん失敗して、よりよい方法をみんなで考えて、病院実習に向けて準備をしています。9月からの病院実習が楽しみです。
文責:小児看護学領域 秋田 由美