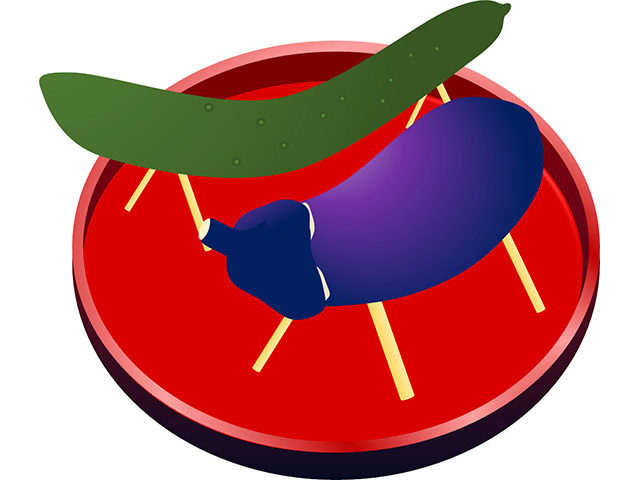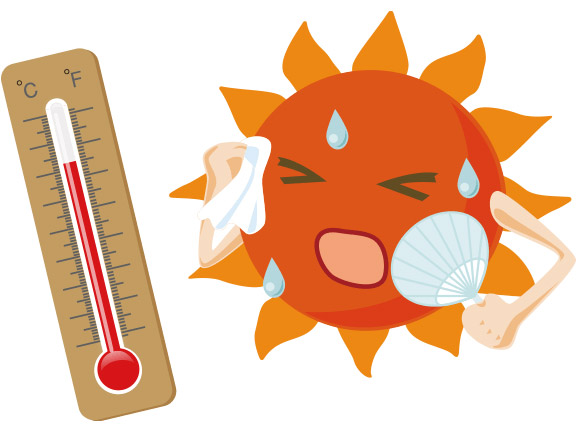『醒睡笑』に描かれた「お彼岸」の風景
2022/03/18
『醒睡笑』(せいすいしょう)という江戸時代の笑い話集があります。元和九年(1623)成立の本作品は、江戸時代の庶民にひろく流布しただけでなく、後世の落語のネタにも大きな影響を与えました。安楽庵策伝(1554-1642)というお坊さんが蒐集したもので、「眠りを醒まして笑う」ほどの面白さから『醒睡笑』という名が付けられました。
今回は『醒睡笑』に収録された「お彼岸」に関する笑い話から日本の文化について考えてみましょう。
「お彼岸」は「春分の日」と「秋分の日」を「御中日」とした前後三日間に営まれる仏教の年中行事で、インドや中国・台湾には見られない日本独自の風習です。そもそも「彼岸」はインドのサンスクリット語「Pāramitā」を訳した言葉(到彼岸)に由来し、仏さまの世界である「向う岸」を意味します。悩み尽きない世界(此岸)から心穏やかな仏さま世界(彼岸)に渡るのが仏教の修行であり、東アジアに伝播した大乗仏教では自分ひとりだけでなく、みんなで一緒に彼岸に渡ることを大切にしました。

駒沢学園・通称「地蔵通り」
それでは『醒睡笑』巻四(内閣文庫本)に収録された「お彼岸」をめぐる主人と家来の口論を簡単に見ていきましょう。
あるお彼岸でのこと、家来は袖を連ね仏さまに手を合わせる風景を目にし、「“ひゅうがん”(ひうがん)なのでお参りが多いですね」とつぶやきました。それを聞いた主人は、「“ひゅうがん”とはひどい片言(なまり)だ。“ひがん”と言いなされ」と注意します。すると家来は「私は生まれてこのかた五十年、“ひゅうがん”と言い慣わしてきました。“ひがん”とはこれまで一度も聞いたことございません」と口答え。いささか意地を張った家来の態度に主人は腹を立て、土地を治める地頭に「彼岸の読み」について裁定を仰ぎました。
地頭は両者の言い分を聞いたうえで「どちらも道理あり」と述べ、次のように諭しました。
「彼岸は春と秋と二度ある。秋は収穫の時期で、月明かりで夜に田を刈るほどの忙しさゆえ、なるべく言葉を短くするのが肝要、“ひがん”と言うのがよろしい。春は四方の山に霞がかかり、小鳥はさえずり、花がなくても一面が芳しく、のどかに蝶は舞い遊び、陽炎も立ちのぼるのんびりした季節である。ならば“ひゅうがん”と言うのがよろしかろう。」
秋の「彼岸」は収穫期の忙しさから言葉短く「ひがん」と、春の「彼岸」はかんばしい花々に蝶たちが舞うように「ひゅうがん」と悠長に……。この解釈がどこから出て来たのか、また、「彼岸」を「ひゅうがん」と言う「片言」がどこの地方のものか定かではありませんが、実に見事なお諭しです。地頭に「どちらも道理あり」と諭された二人の口論は、丸く収まったことでしょう。
「彼岸」に限らず、「片言(なまり)」を題材とした笑い話は『醒睡笑』にいくつか見られます(「石榴」(ざくろ)を(じゃくろ)、「地震」(じしん)を(なゆ)など)。こうした話の結末には、「こちらが正しく、あちらが間違い」と白黒をつける“オチ”は見当たりません。ここで地頭が述べた「どちらも道理あり」という言葉には、双方が歩み寄れる“着地点”を見出そうとする調整力、すなわち、人と人を和ます日本文化の“しなやかさ”が見えてきます。

早春に咲くこぶしの花(駒沢学園構内)
春は大学でも新しい年度がはじまるなど、社会のさまざまなところで新しい生活がはじまります。そして、いろいろな人との出会いが待っています。新たな出会いのなかで、時に「え?」と耳を疑うような言葉や意見と出くわすこともあるかもしれません。そんな時、かの地頭のように「どちらも道理あり」と“しなやか”な応対ができれば、自分も相手も春のようなあたたかな笑みに包まれることでしょう。『醒睡笑』の作者・策伝が思い描く「彼岸」とは、そのような笑みに包まれる風景であると感じます。
山本 元隆