平成28年度「学生のための乳の研究活動支援」研究活動成果報告会において本学科の発表が「食育・栄養指導部門」の最優秀賞に輝きました
2017/01/20
2016年12月11日(日)にベルサール東京日本橋において「学生のための乳の研究活動支援」研究活動成果報告会が開催されました。この研究報告会は、一般社団法人Jミルクが主催するもので、「次世代における乳の学術研究の育成・発展を図ることを目的に、栄養学、教育学、マーケティング等に係る大学の研究室、ゼミ、学生研究団体等が、乳に関連する調査研究活動(食べ物としての「牛乳乳製品」およびそれを生産する産業としての「酪農」「乳業」に関する調査研究等)を行う場合について、その活動費の一部を助成するとともに、発表の場を提供し、優れた研究活動については表彰する」との趣旨で実施されたものです。当研究報告会には、大学生を中心に、研究者や酪農乳業関係者を含む約120人が参加しました。
この研究報告会には、全国15大学18研究室等から21題の演題が出され、①食育・栄養指導部門(11演題)、②乳利用普及部門(3演題)、および③マーケティング部門(7演題)の3つの部門別に発表が行われました。駒沢女子大学健康栄養学科からは、3つの研究室の卒業研究生が口頭発表を行いました。各研究室の発表テーマは、以下の通りです。
| 食育・栄養指導部門 | |
|---|---|
| 田邉研究室 | 「回復期リハビリテーション患者における牛乳乳製品の摂取状況と健康状態の関係」(発表者:石田、細合) |
| 三浦研究室 | 「妊婦のための食事・栄養管理支援ツールの作成とその効果検証」(発表者:竹内、原、平野) |
| 乳利用普及部門 | |
| 西村研究室 | 「乳和食の減塩効果の検証」(発表者:藤掛、山川、山下) |
発表時間は20分間、質疑応答時間は10分間と学術学会と同等の形式で行われ、質疑応答では厳しく激しい議論が交わされました。通常、健康栄養学科では、在学生が卒業研究の内容を学外で発表する機会がないため、今回のような学外での発表と議論の場は、本学科の学生にとって大いに刺激になったようです。
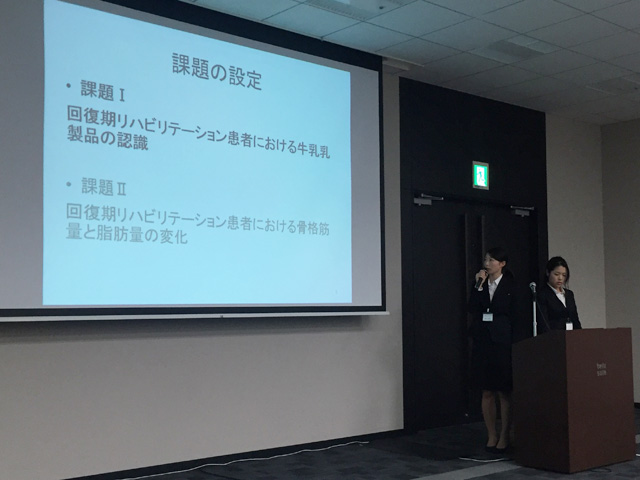
口頭発表の様子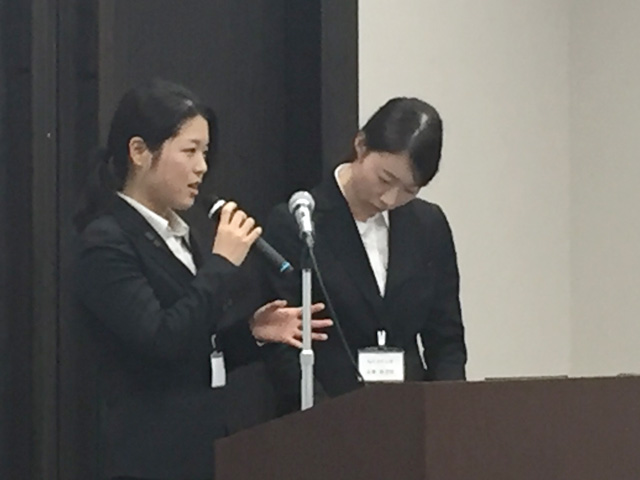
質疑応答の様子
報告会の最後には、乳の学術連合会員による各発表内容の審査が行われ、最優秀賞3題、優秀賞4題が選出されました。健康栄養学科の研究室からは、田邉研究室の演題が食育・栄養指導部門の最優秀賞に選ばれました。他の2演題は、今回は残念ながら入賞には至りませんでしたが、どちらも日頃の成果をしっかりと発揮し、わかりやすく研究発表を行うことができました。最優秀賞に選ばれた田邉研究室の研究内容を以下に紹介します。
回復期リハビリテーション患者における牛乳乳製品の摂取状況と健康状態の関係
石田奈菜絵・細合珠生(駒沢女子大学 健康栄養学科 田邉研究室)
骨折等で入院した患者は、日常生活に復帰するためにリハビリテーション(以下、リハ)を行う。若年者に比べて回復に時間がかかる中高齢者にとって、回復期リハ時の食事はより一層重要になる。一方、牛乳乳製品はタンパク質やカルシウム含有量が高く、病院給食において一般的に提供される食品である。タンパク質やカルシウムは筋肉や骨の構成成分であるため、回復期リハ患者に対する栄養補給としての牛乳乳製品の可能性を検討することは重要である。そこで、本研究では回復期リハ病棟に入院する中高齢者29人(平均78.7歳)を対象とし、牛乳・乳製品の認識と摂取量を調査した。その結果、牛乳乳製品にカルシウムが含まれている認識は高いが、それと比べてタンパク質が含まれている認識は低いことがわかった。また、ヨーグルトは、牛乳に比べるとタンパク質やカルシウムが含まれている認識は低い傾向にあることも示された。さらに、毎朝提供される牛乳やヨーグルトの喫食率は、全対象者で100%と高く、1日に摂取するタンパク質・カルシウムの総量に対する牛乳・ヨーグルトからのタンパク質・カルシウムの摂取割合は、それぞれ10%及び36%と比較的高い割合であった。これらの割合は、喫食率が低い患者ほど高くなることから、牛乳・乳製品は喫食率の低い患者にとって特に大事なタンパク質・カルシウムの補給源になっていることが示唆された。
つづいて、対象者29人の内、3ヶ月間経過観察することができた17人を対象とし、体重、体脂肪量、筋肉量及びADL(activities of daily living:日常生活動作)指標を評価した。結果として、回復期リハ3ヶ月後において、ADL指標の有意な増加、体重と体脂肪量の有意な減少、及び筋肉量の維持が認められた。毎朝の牛乳やヨーグルトの喫食率は全対象者で100%であったため、牛乳・乳製品の摂取が筋肉量の維持にどの程度寄与していたかは明らかにできなかったが、牛乳やヨーグルトを毎朝しっかり摂取し、リハビリの身体活動を3ヶ月間継続して行った対象者では、ADLを高められることがわかった。

最優秀賞を獲得した健康栄養学科4年
田邉研究室の石田奈菜絵さん(左)と細合珠生さん(右)
受賞学生のコメント
- この度は、このような栄えある賞をいただき、日頃の取り組みが成果に結びついたことを大変うれしく思います。今回のこの研究活動は、患者さんのQOLについて深く考えるための大変良い機会となりました。4年生になると就職活動や管理栄養士国家試験に向けた勉強も忙しく、これらと研究活動とを両立することは決して楽ではありません。しかしこの研究を通じて、普段の授業だけでは学ぶことのできない、患者さんや他職種の方々とのコミュニケーションの取り方を学ぶことができ、大変充実した日々を過ごすことができました。大学4年間を振り返り、駒沢女子大学で学ぶことができてよかったと、心から感じています。(石田奈菜絵)
- 卒業研究では、ただ自分の興味のあるテーマに取り組んできただけなのですが、その結果、このような賞をいただくことができ、大変光栄です。この研究を通して、実際の現場で行われている高齢者の健康管理や栄養管理について理解し、より深く考えることができました。また、研究発表にあたっては、統計処理技術や聞き手にわかりやすいプレゼンテーションの技法なども学びました。面識のない大勢の人の前で発表をするというなかなか得られない経験を積み、精神的にも鍛えられたように思います。普段の授業以外でも学ぶ貴重な機会をくださり、また、種々のご指導をいただいた田邉先生はじめ健康栄養学科の先生方に感謝いたします。(細合珠生)


