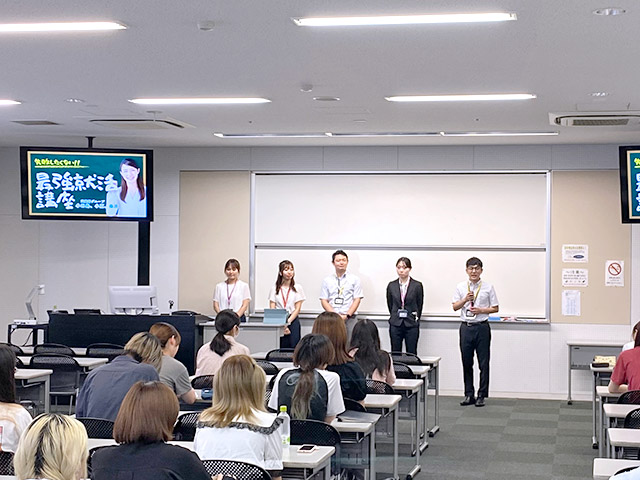フォスタリング機関の方より、児童養護についてお話しいただきました
2025/07/24
さまざまな事情により親元で生活することができない子どもは、東京都内だけでも約4,000人に上ります。そうした子どもたちを家庭に迎え入れ、ともに暮らしているのが「里親」の皆さまです。今回ご講義いただいた多摩児童相談所フォスタリング機関二葉学園(たまふぉす)の方々は、里親制度の普及啓発に加え、里親家庭に迎え入れられた子どもたちと里親の方々を包括的に支援する取り組みを行っています。
心理学科では、公認心理師養成のためのカリキュラムを開講しております。心理実習では、教育センターや少年センターなど、心理学の5領域(保健・医療/福祉/教育/司法・犯罪/産業・労働)に関連する実習先において、公認心理師として必要な知識と技能を養います。また、この心理実習に加えて、すべての学生ではありませんが、3・4年次の心理学ゼミにおいては、事業所や施設などを直接見学したり、実習として参加したりする機会もあります。
2年生のこの時期に、全員が現場でご活躍されている方々から直接お話を伺うことができたのは、大変貴重な経験となりました。現在履修している「児童養護」をはじめとする福祉関連の科目や、今後履修予定の科目とも深く関係する内容を、教科書ではなく現場の声として直接聞くことができたことは、実習に参加する機会のない学生にとっても非常に有意義な機会となりました。
心理学科には、公認心理師を目指している学生だけでなく、児童養護施設や児童福祉に関わる仕事に就くことを目標としている学生も多く在籍しています。そうした学生にとって、今回の講義は大変参考になったことと思います。また、過去にはこの講義を受講したことをきっかけに、実際にボランティア活動に参加した学生もおりました。
つぎに学生の感想を紹介します。
- 今回の授業で、里親制度には深刻で現実的な課題がある一方で、子どもたちを支える尊い魅力もあることを学びました。もし自分が施設で育った子どもだったら、環境の変化にストレスを感じて反発してしまうかもしれません。しかし、職員の方々が一人ひとりの子どもに真剣に向き合い、試行錯誤しながら支えている姿に感動しました。子どもと職員の信頼関係があってこそ支援が成り立っていると感じ、心を打たれました。
- 児童福祉司を目指して心理学を学んでいましたが、最近は一般企業への就職も考えていました。しかし今回の講義を受け、児童福祉司という仕事の素晴らしさを改めて感じ、初心を思い出しました。特に印象的だったのは、里子には明るく前向きな子どもが多いと知り、これまで抱いていた「暗い雰囲気」という先入観が覆されたことです。また、里親の数は増加しているが、すべての児童が委託できるには更なる増加が必要という現状を知り、より多くの人に里親制度を知ってもらう機会を設けることが必要だと感じました。さらに、病院で血縁関係について毎回説明を求められるといった、里親側が抱える心理的負担や不安にも触れ、制度面の理解や支援の必要性を強く実感しました。講義を通して、子どもと里親を取り巻く現状を深く知ることができ、改めて児童福祉に関わる仕事への関心と意欲が高まりました。今後もこの分野への理解を深め、将来に生かしていきたいと思います。
- フォスタリング機関には、5つの里親支援業務があることがわかりました。また、里親の資格は5年ごとに更新することを初めて知りました。子どもが家庭から離れずに済むように家庭を支援し、施設ではなく家庭に近い環境で里親が養育することが重要であり、里親の数も増やす必要があると理解しました。実際の里親や子どもの声から、病院で毎回里親について説明しなければならないことを知り、病院側はあらかじめ理解していると思っていたため驚きました。里親になる人だけでなく、子どもの声にも耳を傾ける必要があると改めて感じました。子どもたちに寄り添っているつもりでも、本当の気持ちを話せない場合があることから、里親だけでなく子どもにも寄り添うことが大切だと思いました。ドラマや映画では知ることができない、実際に働く方の話を聞けて非常に勉強になりました。
たまふぉすの皆さまには、毎年お忙しい中、貴重なお話を賜り誠に感謝申し上げます。