外交官から国際協力の現場を学びました
2016/07/12
国際文化学科 杉野 知恵
国際文化学科専門教育科目の国際貢献論では、政府開発援助(ODA)や平和維持活動(PKO)などのさまざまな国際協力を概観し、日本の国際貢献のあり方について学びます。
授業担当の私が外務省出身ということもあり、学生からは外務省って一体何をするところなのかという質問がよく寄せられます。今学期は、外務省が実施している出前講座(外交講座)から国際協力の最前線で活躍する若手職員を招いて、特別授業を行いました。学生は現場での苦労ややりがいなどを伺いながら、なぜ日本が国際協力を行うのか考えていきます。今回の講師は、外務省の国際協力局でアジア地域への開発協力に携わる塚本剛志先生です。

スペイン語と国際協力の専門家、塚本先生
学生は緊張した面持ちで熱心に耳を傾け、質問の手も積極的にあがりました。講義後の課題ペーパーには、枠いっぱいに意見が書かれており、今回の外交講座は、学生が日本と外国とのつながりを改めて意識し、国際協力に目を向ける良いきっかけとなりました。
学生の感想をいくつかご紹介します。

真剣な表情の学生たち
- 日本の主なニュースでは、政府や国の欠点ばかり取り上げられることが多く、良いニュースが少なく感じられます。メディア報道の情報を取り入れるとき、自分の知識があるかどうかで印象も変わってくると思います。日本と途上国の関係を築き、国境を越えて、助け合っていけるということ、日本だけが助けるのではなくて、途上国も私たちを支えてくれているという認識が広がっていくことが大切だと考えます。(3年MKさん)
- 武力ではなく、自然災害など環境問題で困ったときに助け合える国際関係は理想的だと思った。それが互いの国の利益になって、どの国も発展していけたらいいのにと思った。同時に、それは自国の利益、世界各地での紛争、北朝鮮のことなどを考えるとまだまだ難しいことだと思った。(3年MTさん)
- 過去に日本は援助される側であったのは知っていましたが、現在日本が数多くの国に対して行っている開発援助・支援活動の内容を知ることができたのは印象深いことでした。特に感銘を受けたのは、南アジアのモルディブから東日本大震災後に支援を受けたことです。国益以外にも大事なことがあることを感じ取れましたし、このような国に行ってみたいという気持ちが湧いてきました。(3年MHさん)
- 国際協力を通じて自国を守る意味、日本が世界から評価される意味、また日本国内の技術開発を活かす道を知ることができた。外務省だけでなく、他の省庁と協力してODAが遂行され、長いプロセスを経て一つのプログラムが完成していくのだとわかった。(3年MTさん)
- 日本が第二次世界大戦後に国際協力による支援で経済大国になったことから、現在支援を受けている国にも経済的に良くなるきっかけができればよいとは思います。しかしそれが幸せにつながるかと言うと、それも違うと考えているので、見た目の豊かさと心の豊かさの倫理的問題に関して、私には煮え切らない部分もあります。(3年AKさん)
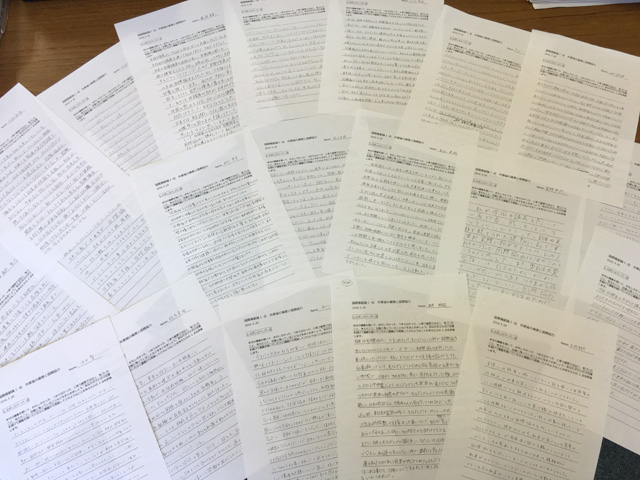
学生からの熱いコメント!
講義を終えた塚本先生からは、「学生から良い質問がたくさん出て、真剣に聞いてくれたことがよくわかりました。」とコメントがありました。
外交講座の様子は、外務省のホームページにも紹介されています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/dpr/page25_000388.html


