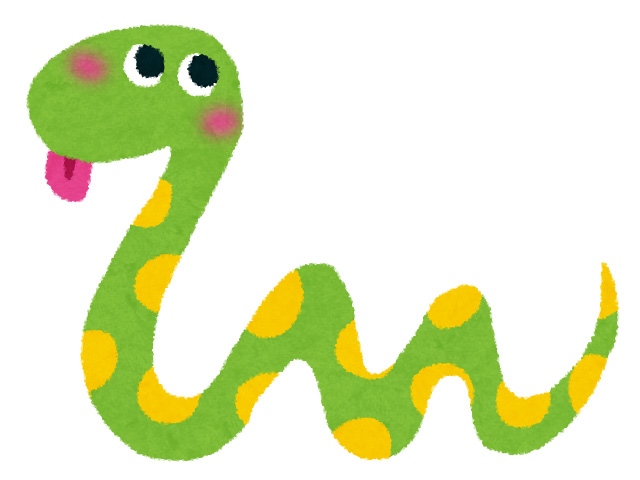これから進学するみなさんへ[国語科 新村]
2025/01/16
今年はへび年。へびにまつわる思い出がある。
小学校のころ、学校で山登りに行ったときのことだ。腕に虫に刺された跡を見つけ、「あ、かまれた。」と言った。一緒にいた友達がびっくりして「何に? へび?」と声をあげた。「たぶん、蚊だと思う。」と言うと、「何言ってんの? 蚊はかまないよ。刺すんだよ。」と言い返されて驚いた。私の家では大人たちが「蚊にかまれる」というのだ。違いにとまどうよりも、面白いと思った。後に「蚊にかまれる」というのは西の方の言い方であり、東京で育ったが、親族が東京出身ではない私は自分でも知らずに方言に触れていたとわかった。
大学生になって、国文学・国語学を専攻する中で、方言学の講義と演習を受講した。演習では、各自が出身の地方または調査可能な地方の方言を調べて発表することになっていた。私は奄美大島の方言について、出身である祖母から聞き取り調査をすることにした。大学には全国から学生が集まっていて、発表では日本各地の方言が披露され、その独自性と多様性に圧倒され、「日本は広いな」と思った。
もちろん、学問として調査をするので、動詞や形容詞の分析が中心になるのだが、一番盛り上がったのは川端康成の「雪国」の冒頭部分の各方言訳だ。方言は話し言葉であるのに、書き言葉である小説を方言にするのには無理があるが、この方法なら同じ文を各地方でどのように言い換えるのか、比較ができるのだ。例えば、冒頭の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という部分は、鹿児島県指宿市編では「国境ノ長カトンネルオ抜クット雪国ジャッタ。」となるそうだ。みんな家族や知り合いに相談しながら取り組んでいた。ところが、私はこの課題ができなかった。祖母がどうしても訳せないというのだ。まず、奄美大島では雪があまり降らない。『雪国』の冒頭は汽車から降りた場面で「駅長さん」が出てくるが、そもそも奄美大島には電車が通ってないので、「駅長」にあたる言葉もない。「襟巻(マフラー)をして」という部分では「奄美ではよっぽどおしゃれじゃないと、マフラーなんて持ってない。」と祖母が怒り出してしまった。困り果てて教授に相談すると、私だけ夏目漱石の『吾輩は猫である』の冒頭部分を訳すことになった。少しだけ紹介しよう。「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」の鹿児島県大島郡宇検村久志編は「ワンナ猫(ミャー)ジャッパ。名(ナー)ヤナマネン」となるそうだ。訳してくれた祖母は大変だっただろうが、孫に方言を伝えるのは楽しかったと言ってくれた。
発表を通して言葉という視点から日本各地の人びとの暮らしぶりを感じ取れたような気がして興味深かった。一つの切り口を深く探っていくと、そこから世界が広がったり、他と繋がったりする経験ができる。それが学ぶということの醍醐味ではないだろうか。これから進学する生徒さんたちには、それぞれが興味のあることを深め、世界を広げていってほしいと思う。
国語科 新村